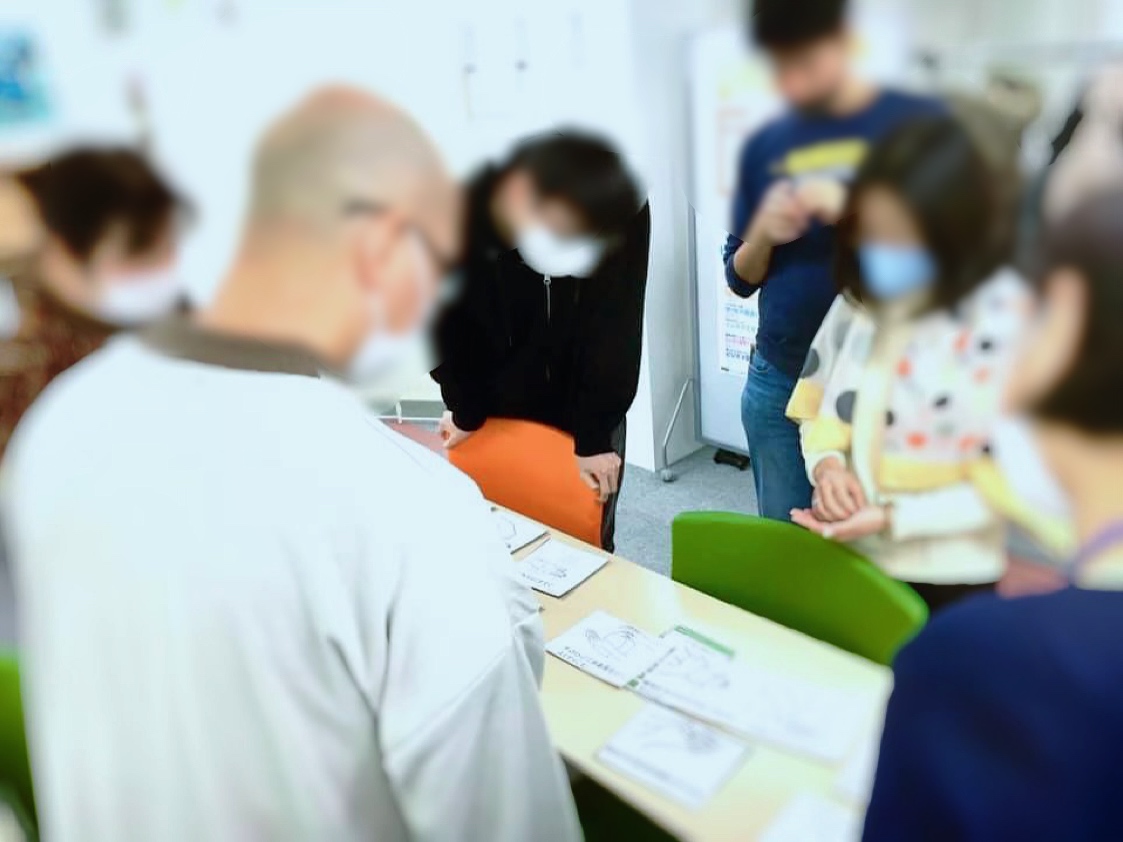「覚えられないのは私だけ?」発達障害のある方が仕事を覚えるためにできること
新しい職場、新しい仕事。がんばって覚えようとしているのに、何度やってもミスをしてしまう。周りの人たちがスムーズにこなしている中で、「どうして私はできないんだろう…」と自分を責めてしまうことはありませんか?
発達障害のある方の中には、特性の影響で仕事の手順や段取りがなかなか頭に入りづらかったり、記憶に定着しにくかったりする方が少なくありません。でも、それは“努力不足”ではなく、脳の情報処理の仕方に違いがあるだけなのです。
この記事では、「仕事が覚えられない」と感じている発達障害のある方に向けて、困りごとの背景や、実際に役立つ対処法について詳しくご紹介します。自分の特性を理解しながら、少しずつでも「できる」を増やしていけるように、サポートのヒントをお届けします。

なぜ仕事が覚えられないのか?発達障害の特性による影響
目次
発達障害とひとことで言っても、その特性は人によってさまざまです。なかでも、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)の特性を持つ方は、以下のような傾向から「仕事が覚えにくい」と感じやすいことがあります。
- 一度に複数のことを処理するのが苦手
→ マルチタスクや、臨機応変な対応が求められる場面で混乱しやすい - 指示の意図を正確に把握しづらい
→ 言葉のニュアンスや背景の理解に時間がかかる - ワーキングメモリが弱い
→ 一時的な情報(手順や段取り)を覚えておくのが苦手 - 感覚過敏や注意の切り替えの難しさ
→ 周囲の音や刺激に気を取られ、集中が続かない
こうした特性は「障害」ではなく、情報処理の“スタイルの違い”とも言えます。つまり、“合わないやり方”を無理に続けるのではなく、“合うやり方”を見つけていくことが重要なのです。
よくある「つまずきポイント」とその背景
仕事を覚えるプロセスの中で、発達障害のある方がつまずきやすいのは、以下のような場面です。
- マニュアルが口頭説明のみで終わるとき
→ 視覚的な情報がないと記憶に残りにくいケースがある - 毎回少しずつやり方が変わるとき
→ 一度覚えた手順に固執し、柔軟な対応が難しくなることも - 「見て覚えて」と言われたとき
→観察だけで手順を把握するのが困難な場合がある - 作業の優先順位が明示されていないとき
→ どの作業から始めてよいか分からず、パニックになることも
これらは「理解力がない」からではなく、見せ方・伝え方の相性の問題です。情報の受け取り方に合った方法を工夫することで、つまずきを減らすことができます。
覚え方に工夫を取り入れる|具体的な5つの対策
1. 手順を視覚化する
仕事の流れややることを、図やリストなど“見える形”で整理することで、記憶への定着が高まりやすくなります。例えばチェックリスト、フローチャート、イラスト付きマニュアルなどが効果的です。
2. 反復学習を意識的に取り入れる
「繰り返すこと」が苦手な方もいますが、定着には反復が重要です。短時間でも毎日少しずつ確認する、同じ作業を続けて担当させてもらうなどの方法が有効です。
3. 音声メモや写真で記録を残す
自分にとって覚えやすい形式を選びましょう。作業工程をスマホで録音したり、手順の一部を写真に残しておくことで、見返して確認できるようになります。
4. ひとつずつ覚える
一度に多くのことを覚えようとせず、「今日はこれだけ」「この作業に集中する」といった段階的な習得を目指すと、混乱を防げます。
5. できないことを言語化しておく
「どこがわからなかったのか」「どの部分で混乱したのか」を、自分なりに書き出しておくことで、フィードバックを受けたり支援を求めやすくなります。
環境の影響も大きい|職場との相性を見直す視点
仕事が覚えられないとき、「自分に問題がある」と考えてしまいがちですが、実は職場の環境との相性も大きく影響します。
- 丁寧に教えてくれる風土かどうか
- 視覚的なマニュアルや研修制度が整っているか
- 質問しやすい雰囲気があるか
- 一人ひとりのペースを尊重してくれる文化か
このような点を事前に確認できると、働きやすさがぐっと変わります。見学や実習などの機会を活用して、環境とのマッチングを丁寧に行うことも重要です。
「できない」は悪いことではない|自分を責めすぎないために
「何度言っても覚えられない」「メモを取っても混乱する」──そうした経験を繰り返すと、自信を失ってしまうこともあります。しかし、それはあなたの価値を否定するものではありません。
得意・不得意は誰にでもあり、発達障害のある方にとっては「覚えづらさ」がその一部であるだけ。工夫や支援によって乗り越えられるものも多く存在します。
まずは「覚えられないのは私だけ」と思い込まず、「どうしたら覚えやすくなるか」を一緒に考えていくことから始めてみませんか?
必要なサポートを受けながら働き方を見つける
覚えにくさや働きづらさを感じたとき、一人で抱え込まずに外部の支援機関や専門家の力を借りることも重要な選択肢です。
例えば、発達障害に理解のある支援機関では、あなたの困りごとに合わせたサポートやトレーニングを受けることができる場合があります。また、職場でのトライアルや適職探しの相談なども可能です。
就労は“ゴール”ではなく、“過程”です。焦らず、少しずつ“自分らしい働き方”を見つけていきましょう。
仕事を覚えるのがつらいときに見直したいチェックリスト
―「覚えられない」を減らすための気づきと工夫―
□ 自分の覚えやすいスタイルを把握できていますか?
- ☐ 図や写真など、視覚的に理解する方が得意
- ☐ 話を聞いて理解するほうが得意
- ☐ 書きながら覚えると定着しやすい
- ☐ 身体を動かして体感することで覚えやすい
□ 仕事の手順や情報を「見える化」していますか?
- ☐ 手順書やチェックリストを使っている
- ☐ 自分なりのメモやノートにまとめている
- ☐ スマホのカメラや録音を活用している
- ☐ 重要なことは付箋などで視覚的に強調している
□ わからないことを整理・言語化できていますか?
- ☐ どの場面で混乱するのかを振り返っている
- ☐ 上司や同僚に質問できる環境がある
- ☐ 「わからないことリスト」を作っている
- ☐ 周囲に伝えやすい言葉でまとめている
□ 自分に合った“反復”ができていますか?
- ☐ 1回で覚えられなくても気にしすぎないようにしている
- ☐ 同じ作業を繰り返すチャンスをもらっている
- ☐ 毎日少しずつ確認する習慣がある
- ☐ 「今日はここまで覚える」とゴールを分けている
□ 環境の影響について考えたことがありますか?
- ☐ 作業環境が静かで集中しやすい
- ☐ 自分のペースで学べる体制がある
- ☐ 職場に特性への理解がある
- ☐ ミスを責められず、フォローしてもらえる
□ 無理せずサポートを求める姿勢を持てていますか?
- ☐ ひとりで抱えこまないようにしている
- ☐ 第三者に相談する窓口を知っている
- ☐ 訓練や支援の場を検討したことがある
- ☐ 自分を責めすぎず、できたことに目を向けられている