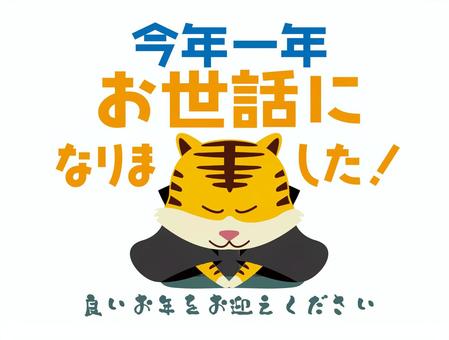転職してから心がつらい…うつ病を疑ったときに知っておきたい5つの選択肢
新しい環境に身を置くことは、本来であれば前向きな一歩であるはずです。しかし、転職後に「なぜか気分が沈みがちになった」「朝起きるのがつらくなった」「自分を責める思考が止まらない」といった不調を抱える方は少なくありません。
「これくらいで弱音を吐いてはいけない」と我慢を続けた結果、気づけば心身のバランスを崩してしまう——これは珍しい話ではなく、転職を機にうつ病を発症するケースは近年増加傾向にあります。
本記事では、「転職 で うつ 病」という検索キーワードに基づき、転職後に感じる心の不調がうつ病かもしれないと感じたときに取るべき5つの具体的な選択肢について解説します。早期の気づきと適切な対応が、再び安心して働くための第一歩になります。

1. 医療機関での受診をためらわない
目次
うつ病は、医学的に明確な診断基準のある疾患であり、決して気の持ちようや甘えではありません。診断が遅れれば遅れるほど症状が慢性化し、回復までに長い時間がかかる可能性もあります。
特に以下のような症状が2週間以上続いている場合は、医療機関の受診を検討すべきサインです。
- 朝起きるのが極端につらく、会社に行けない
- 集中力や思考力が低下し、業務が手につかない
- 食欲の低下、過食、睡眠の乱れがある
- 自分を過度に責める思考が止まらない
- 楽しかったことに関心が持てなくなった
受診先は、精神科や心療内科が適切です。初診時には、いつからどのような不調があるのか、転職によって何が変わったのかを時系列で伝えると、正確な診断が得られやすくなります。診断が確定すれば、必要に応じて薬物療法や認知行動療法などが提案され、治療の方向性が定まります。
2. 「我慢して働き続ける」以外の道を知る
うつ病を疑いながらも、「職場に迷惑をかけたくない」「また転職するのは避けたい」と無理に勤務を続ける方が多くいます。しかし、心身のバランスを崩した状態での就労継続は、パフォーマンスの低下や対人トラブル、さらなる悪化を招くリスクがあります。
医師の診断をもとに、休職を選択することは「逃げ」ではなく「治療の一環」です。特に労働契約上、休職制度が整備されている企業であれば、一定期間の休養を経て職場に復帰する道も用意されています。休職中の過ごし方や公的手当(傷病手当金など)については、医療機関や社会保険労務士に相談することで、経済的な不安を軽減することが可能です。
また、すでに退職を選んでしまった場合も、「次にどう動くか」を焦らずに考える時間を確保することが大切です。治療とリカバリーに専念することは、将来の安定した就労につながる重要なステップです。
3. 就労準備をサポートする外部支援を活用する
うつ病の治療と並行して、「また働けるようになるための準備」を段階的に行うことは、再発リスクの軽減にもつながります。その際に有効なのが、就労に困難を抱える方を対象とした専門的な支援制度の活用です。
たとえば、就労移行支援制度では、以下のようなプログラムを通じて再就職の準備を支援しています。
- 日中の活動リズムの安定化
- ストレス対処法や自己理解を深める訓練
- 模擬業務や職場実習を通じた職業適性の把握
- 履歴書・職務経歴書の作成支援
- 面接練習や企業とのマッチング支援
- 職場定着のためのアフターケア
特にうつ病からの回復過程にある方にとって、段階的なリハビリ的支援は、焦らずに「働ける自分」を取り戻すうえで効果的です。多くの支援機関では見学や体験利用も可能なので、ハードルを下げて情報収集から始めてみることをおすすめします。
4. 職場環境のミスマッチを再評価する
転職によって心身の不調が出た場合、その背景には「職場環境との相性」が関係している可能性があります。うつ病の直接原因は多因子的であるものの、下記のような環境要因は大きなストレス要素となり得ます。
- 高圧的なマネジメントやパワハラ
- 慣れない職種・業務内容への過度なプレッシャー
- 曖昧な指示や評価基準
- 休憩の取りづらい雰囲気や長時間労働
- 対人関係の断絶や孤立感
自身の特性や価値観と職場環境の間に大きなズレがある場合は、「自分が悪い」と考えるのではなく、「環境が合わなかった」と視点を変えることが重要です。就職活動の際には、自分に合った働き方や職場文化を見極める視点が必要であり、そのためにも専門家と共に自己理解を深める機会を持つことが望まれます。
5. 社会資源や制度を正しく理解して使う
うつ病によって仕事を継続できない、あるいは再就職が難しいと感じる方にとって、社会資源や制度の活用は回復を支える大きな支柱になります。代表的な制度や支援は以下のとおりです。
- 傷病手当金(健康保険加入者が休職中に一定期間受給可能)
- 精神障害者保健福祉手帳(就労時の配慮や雇用枠の利用に有効)
- 自立支援医療(通院医療費の自己負担軽減)
- 障害年金(一定の障害状態がある場合に支給対象)
また、上記に加えて、職業リハビリテーションや地域の障害者就業・生活支援センターなど、状況に応じた支援窓口も存在します。情報の把握が難しい場合には、地域の相談支援専門員や医療ソーシャルワーカーなど、制度に精通した専門職に相談することをおすすめします。
まとめ
転職後の不調が続くと、「また失敗してしまったのではないか」「自分は社会不適合なのか」と自責的になる方が多くいます。しかし、うつ病は誰にでも起こり得るものであり、早期の対処によって回復の見込みは十分にあります。
医療機関の受診、働き方の見直し、就労支援の活用、制度の理解と利用——こうした選択肢を一つずつ検討することで、再び安心して働ける道が開けてきます。自分のペースで、一歩ずつ進んでいけるよう、必要な支援をためらわずに取り入れていきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 転職後に気分が落ち込みやすくなりました。これはうつ病の可能性がありますか?
はい、可能性があります。うつ病の初期症状には、気分の落ち込み、意欲の低下、睡眠や食欲の変化、自己否定感などがあります。特に、転職という大きな環境変化のあとにこうした症状が継続している場合は、早めに精神科または心療内科で相談することをおすすめします。
Q2. 転職が原因でうつ病になることはよくあるのでしょうか?
珍しくありません。新しい人間関係、業務内容の変化、自己評価へのプレッシャーなど、転職後のストレス要因は多岐にわたり、もともと心の不調を抱えていた人が悪化するきっかけになることもあります。早期の対処が重要です。
Q3. うつ病で退職したあと、また働けるようになるのでしょうか?
多くの方が、適切な治療と段階的なリハビリテーション支援を通じて再就職を果たしています。無理に急がず、生活リズムの安定や自己理解の深まりを経て就労準備を整えることが、再発予防にもつながります。
Q4. うつ病があっても使える就労支援制度はありますか?
はい。医師の診断書があれば、就労移行支援や障害者雇用支援、職業リハビリテーション制度などを活用できます。精神疾患に特化した支援機関もあり、通所しながら就職準備を進めることができます。
Q5. 転職を繰り返していることが履歴書で不利になるのではと心配です。
一見ネガティブに見える職歴でも、体調管理や働き方の工夫を重ねてきた過程を整理して伝えられれば、誠実な姿勢として評価されることもあります。支援機関などで面接対策や職務経歴書のサポートを受けることで、適切なアピールにつなげることが可能です。