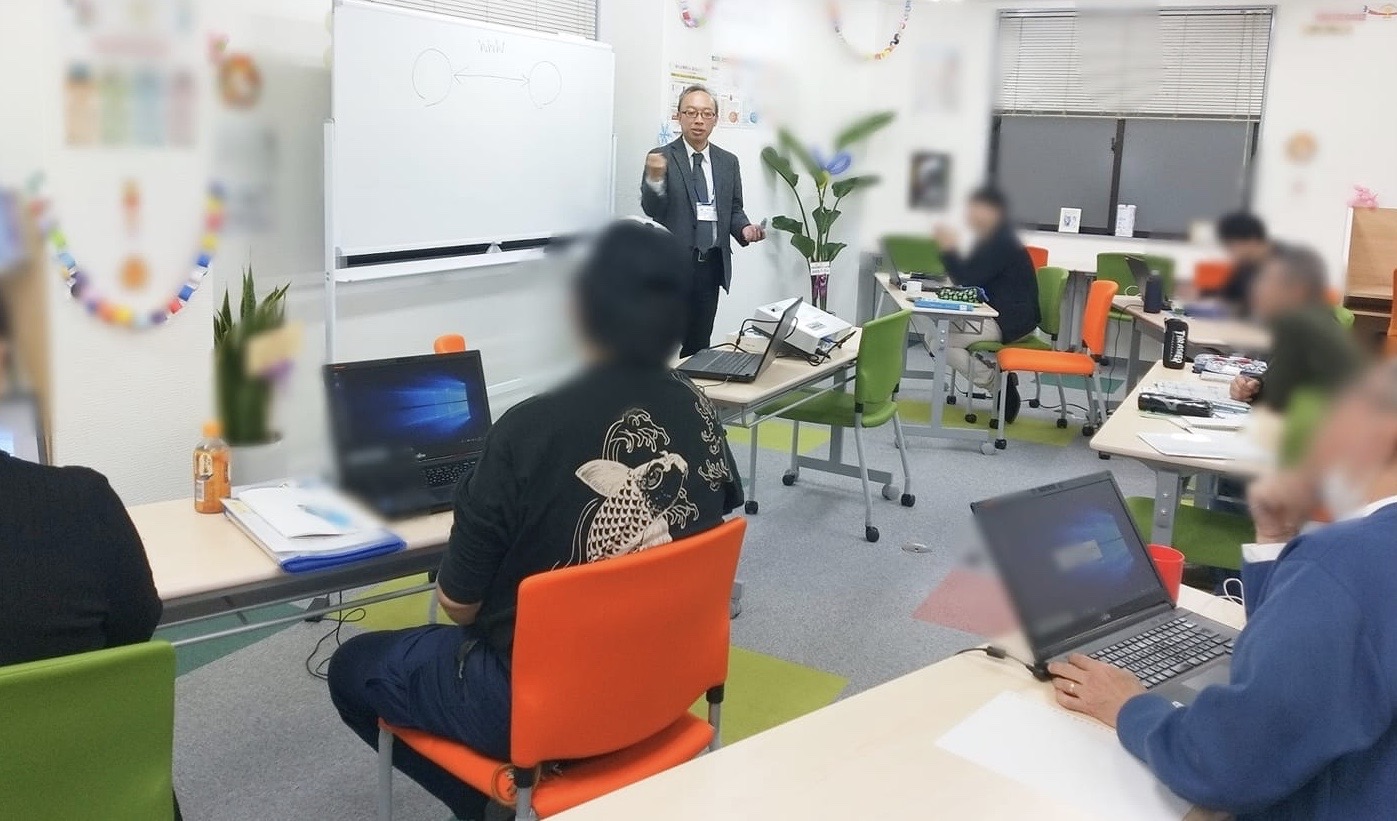【適応障害】復職後に休みがちになる原因と対策|再休職を防ぐためのポイント
適応障害の治療を経て復職したものの、「思うように働けない」「休みが増えてしまう」と悩む方は少なくありません。復職後の安定は、症状の回復だけでなく、職場環境や働き方の調整、周囲の理解など、さまざまな要素が影響します。適応障害は一度回復したように見えても、再発や再休職のリスクが比較的高いとされており、慎重な対応が必要です。本記事では、「復職後に休みがちになる原因」と「再休職を防ぐための具体的な対策」を、専門的な観点から詳しく解説します。

復職後に休みがちになる主な原因
目次
適応障害は、特定のストレス要因が引き金となって発症します。そのため、症状が落ち着いても、復職後に同じストレス環境に戻ることで再び不調が表れることがあります。復職直後は心身の負荷が大きく、次のような原因が重なることで休みがちになるケースが多いです。
まず、職場復帰に伴う「環境変化への再適応」が大きな負担となります。長期間の休職を経て復職すると、業務内容や人間関係、職場の雰囲気などが微妙に変わっていることがあります。その変化に順応しようとする過程でエネルギーを消耗し、体調を崩すことが少なくありません。
また、「自分は以前のように働けなければならない」というプレッシャーも大きな要因です。責任感が強い人ほど無理をしてしまい、疲労の蓄積に気づかないまま不調が再燃するケースがあります。さらに、職場側の理解が十分でないと、配慮が得られず負担が増加し、休みがちになる傾向が見られます。
無理な働き方の再開が再発の引き金になる
復職直後に「以前と同じ働き方をすぐに再開する」ことは、再発の大きなリスク要因です。適応障害は一見症状が落ち着いていても、ストレス耐性や集中力、体力は完全に回復していない場合が多く、急激な業務負担の増加は心身の不調を引き起こしやすくなります。
特に、残業や繁忙期対応、複数業務の並行処理といった高負荷な働き方を再開すると、短期間で疲弊してしまうことがあります。また、「周囲に迷惑をかけたくない」という気持ちから、自分の限界を超えて働いてしまう人も少なくありません。
復職初期は「フルパフォーマンスを目指す」時期ではなく、「安定したリズムを取り戻す」時期です。段階的な業務復帰や柔軟な働き方の導入が、再発予防に欠かせません。
体調とメンタルの波を見極めることの重要性
適応障害の回復期には、日によって体調や気分に波があるのが一般的です。調子の良い日が続いた後に急に不調がぶり返すことも珍しくありません。これは決して意志が弱いわけではなく、脳や心身がストレスに慣れていない段階であるためです。
そのため、復職後は「体調の波を把握する」ことが非常に重要になります。日々の体調や感情の変化を記録することで、自分のペースや限界が見えてきます。これにより、無理をする前に早めに休息や調整を行うことができ、不調の長期化を防げます。
また、復職初期に無理をしてしまうと、「休んではいけない」「また迷惑をかけてしまう」といった思考が強まり、かえって休みづらくなることもあります。休むことをネガティブに捉えず、早期の調整を「再発予防の一環」と位置付けることが大切です。
周囲とのコミュニケーション不足も影響する
復職後に休みがちになる背景には、職場とのコミュニケーション不足が潜んでいる場合があります。特に、上司や同僚との間で「業務量」「体調の状態」「必要な配慮」などについての共通認識が十分に形成されていないと、誤解やすれ違いが生じやすくなります。
たとえば、「もう元気になったのだから普通に働けるだろう」と周囲が思い込んでいるケースでは、配慮が得られず、負荷が急激に高まってしまうことがあります。逆に、本人が「うまくやらなければ」と思い込み、体調の悪化を伝えないまま働き続けると、結果的に長期の休みに繋がることもあります。
日々の小さな変化や体調の揺らぎを共有しやすい雰囲気づくり、業務の優先順位や分担の明確化など、定期的なコミュニケーションが安定した復職には欠かせません。
再休職を防ぐための実践的な対策
復職後に休みがちになる状況を放置すると、再休職につながる可能性があります。再休職を防ぐためには、以下のような実践的な対策が有効です。
まず、「段階的な勤務ペースの調整」を行いましょう。最初からフルタイムで業務をこなすのではなく、体調や集中力に合わせて、業務量や時間を段階的に増やしていくことが望ましいです。
次に、「業務内容の明確化と優先順位付け」が重要です。曖昧な業務範囲や過度な負担は不安や疲労の原因になります。上司やチームと協議しながら、取り組むべき業務を明確にすることで、無理のない働き方が可能になります。
さらに、「生活リズムの安定化」も欠かせません。睡眠・食事・休息といった基本的な生活習慣を整えることは、メンタルの安定にも直結します。休日も含めて一定のリズムを保つことで、体調の波を小さくできます。
必要に応じて、医療機関やカウンセリングなどの専門的なサポートを併用し、自分に合った働き方を模索することも再発予防に役立ちます。
復職後は「完璧さ」ではなく「安定」を重視する
復職後の目標は「以前と同じ働き方をすぐに取り戻す」ことではなく、「安定した働き方を少しずつ築いていく」ことです。適応障害の回復は段階的であり、焦ってしまうと再発のリスクが高まります。
職場に完全に適応するまでには時間がかかるのが自然な流れです。小さな成功体験を積み重ねることで自信を回復し、働くペースを自分の心身に合わせていくことが、長期的な職場定着の鍵となります。
また、復職後に休みがちになることは、決して珍しいことではありません。自分を責めず、体調や状況を客観的に見つめながら、必要なサポートや調整を行っていくことが大切です。
このように、適応障害の復職後に休みがちになる背景には、環境・心理・体調など複数の要因が複雑に絡み合っています。焦らず、一つひとつの要素を丁寧に整えていくことが、安定した就労への近道です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 適応障害で復職したのに、また休みがちになるのはよくあることですか?
A. はい、適応障害では復職後に一時的な体調の波が起こることは珍しくありません。復職初期はストレス耐性や集中力が完全には戻っていないため、再び環境に適応する過程で休みが増えることがあります。焦らず、自分のペースを整えることが重要です。
Q2. 復職後に休みがちになった場合、職場にどう伝えるのが良いですか?
A. 「体調の波があるため、安定して働けるように調整したい」と前向きな姿勢で伝えるのが効果的です。業務量や勤務時間の調整、体調の変化の共有など、具体的な対応策をあわせて話すことで、職場側も理解・協力しやすくなります。
Q3. 無理して出勤を続けた方がいいのでしょうか?
A. 無理を続けることは再発や再休職のリスクを高めます。適応障害の回復過程では「安定」を優先することが大切です。体調が悪い日は早めに休養を取り、長期的に働き続けるためのバランスを取る方が、結果的に職場定着につながります。
Q4. 再休職を防ぐために、自分でできることはありますか?
A. はい、生活リズムを整える、体調の記録をつけて波を把握する、業務の優先順位を明確にするなどが有効です。また、復職後は「以前と同じペース」に戻そうとせず、段階的に慣らしていく姿勢が再発予防に役立ちます。
Q5. 休みが続いた場合、また休職になってしまうのでしょうか?
A. 休みが一定期間続いたからといって、すぐに休職になるとは限りません。ただし、状況を放置すると再休職の可能性が高まるため、早めに医療機関や職場と連携して対策を講じることが大切です。無理を避け、客観的な支援を得ることで再休職を防ぎやすくなります。