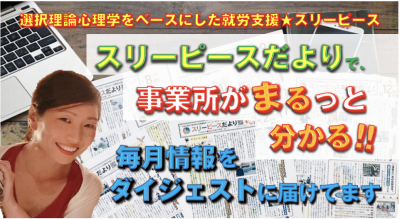仕事が続かない発達障害のある方へ|職場選びと働き方の見直しポイント
「仕事が続かない…」その悩みには理由があります
目次
発達障害のある方にとって、「仕事が続かない」という課題は、単なる気持ちや根性の問題ではありません。集中力、ワーキングメモリ、感覚過敏、人間関係の調整など、日常生活や就労場面で直面する困難さには、脳の認知機能の特性が深く関わっています。
「また辞めてしまった」「自分には働く力がないのかもしれない」と、自責の念にかられてしまう方も多いですが、それは決して能力の問題ではなく、環境や働き方との“ミスマッチ”によって起こっているケースが少なくありません。
この記事では、発達障害のある方が仕事を続けるうえでつまずきやすい背景を整理しながら、職場選びや働き方を見直す際に意識しておきたいポイントを解説します。自分らしく働き続けるためのヒントとして、お役立ていただければ幸いです。

発達障害のある方が仕事でつまずきやすい主な要因
発達障害には主に、注意欠如・多動症(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害(LD)などの分類があります。それぞれ異なる特性を持つ一方で、職場で共通してつまずきやすい傾向も見られます。
- 情報処理の速度や方法の違い
複数のタスクを並行して処理することが難しかったり、口頭指示を記憶・理解するのが苦手な場合があります。 - 対人関係のストレス
曖昧な表現や暗黙のルールを理解するのが難しく、人間関係での誤解や孤立を招くことがあります。 - 感覚過敏や環境負荷への弱さ
音・光・温度などの刺激に過敏で、長時間の勤務や人混みが大きなストレスとなる場合もあります。 - 自己肯定感の低下と疲弊
過去の失敗経験や周囲との比較により、自己評価が低下しやすく、努力が続かない悪循環に陥ることがあります。
これらの要因は「意欲がない」「協調性がない」などと誤解されがちですが、実際には特性と環境の不一致によるものが大きく影響しています。
職場環境が合っていないことが「続かない原因」かもしれない
発達障害のある方にとって、働きやすさは仕事内容よりも環境との相性に大きく左右されます。
たとえば、次のような職場環境では、特性に配慮されないまま働くことで、知らず知らずのうちに大きな負荷がかかり、短期離職につながりやすくなります。
- 業務の指示が曖昧で属人的
- 急な変更やイレギュラー対応が多い
- 周囲が慌ただしく、集中しにくい
- 助けを求めるタイミングがつかみにくい
- 成果よりも“空気を読む力”が重視される
こうした環境で「うまくいかない」と感じたとしても、それはあなたの能力不足ではありません。あくまで、自分の特性に合わない環境だったという見方が重要です。
続けやすい職場の特徴とは?
仕事を長く続けるには、自分の特性と合致する環境を見極めることが鍵となります。以下は、発達障害のある方にとって比較的働きやすいとされる職場の特徴です。
- 業務内容やルールが明確に可視化されている
(マニュアル・チェックリスト・スケジュールがある) - 静かで落ち着いた作業空間が確保されている
(パーティションやノイズキャンセリングなど) - 急な対応やマルチタスクが少ない
(ルーチン業務中心、個人作業がメイン) - 特性に理解のある上司や同僚がいる
(困りごとを話しやすい雰囲気がある) - 小規模で、顔が見える範囲の人間関係
(過剰なコミュニケーションが求められない) - 週3日~など、柔軟な働き方が選べる
(短時間勤務・在宅・職務内容限定など)
こうした条件の職場を選ぶことで、「働き続けること自体のハードル」を下げ、安心して業務に取り組むことができるようになります。
働き方の工夫でストレスを軽減する
たとえ理想の職場にすぐ出会えなくても、自分なりに働き方を工夫することで、ストレスや失敗のリスクを軽減することは可能です。
以下に、実際に取り入れやすい工夫をいくつかご紹介します:
- 視覚的に仕事を整理する
ToDoリストやタイムスケジュール、作業チェック表などを活用し、「何をすればいいのか」を常に可視化する - わからないことをそのままにしない
聞きづらさを感じるときは、メモや付箋を使って質問のタイミングを自分で作る - タスクの優先順位を色や番号で管理する
自分なりの判断基準を持つことで、パニックを防ぎやすくなる - 疲れすぎない働き方を意識する
昼休みに一人になれる場所を確保する、短時間勤務から始めるなど、リズムの調整がポイント - 失敗を記録し、改善策を一緒に考える
失敗そのものよりも「次どうするか」を残すことで、自己肯定感を保ちやすくなる
無理をすることなく、自分の特性に合った“安全な範囲”でのチャレンジを積み重ねていくことが、長く働き続けるための鍵になります。
転職を検討する際の視点と準備
「今の仕事がどうしても合わない」「次こそは長く働ける環境を見つけたい」と感じている方は、転職を選択肢の一つとして冷静に見直してみるのもよいタイミングかもしれません。
転職を検討する際には、次のようなポイントを整理しておくとよいでしょう:
- これまで「うまくいかなかった」具体的な理由
- 「逆に楽だった」「安心できた」場面の共通点
- 働くうえで譲れない条件(勤務時間・通勤・仕事内容など)
- 自分の特性(得意・不得意)をどう伝えるか
また、求人情報を見る際は、「職種」だけでなく「社風」や「働き方」まで注目することが大切です。
可能であれば、実習・見学・体験などを通じて、実際の職場の雰囲気を体感してみると、ミスマッチを防ぎやすくなります。
自分に合った働き方を見つけることが、安定した就労への第一歩
発達障害のある方にとって、就労のゴールは「フルタイムの正社員として完璧に働くこと」ではありません。
むしろ、「安心して続けられる仕事を、自分のペースで積み重ねていくこと」のほうが、長期的には安定した働き方に繋がります。
仕事が続かないことは、恥ずかしいことでも、あなたが社会に向いていない証でもありません。
その背景にある要因を見つめ直し、「どんな働き方なら自分らしく働けるか」を考えることができれば、必ず次の選択肢が見えてきます。
職場に合わせるのではなく、**「自分に合う職場を選ぶ」**という視点を持つこと。
それが、自分を守りながら働く第一歩になります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 発達障害があると、本当に仕事を長く続けるのは難しいのでしょうか?
A. 発達障害のある方が就労を継続する上で困難を感じやすいのは事実ですが、それは個人の能力や意欲の問題ではなく、環境との相性による部分が大きいです。自分の特性に合った職場環境や業務内容を見極めることで、長期的な就労も十分に可能です。
Q2. 過去に短期間で離職を繰り返しています。次の就職活動で不利になりますか?
A. 職歴の多さに不安を感じる方も多いですが、発達障害の特性や過去の経験を通じて「何が自分に合わなかったのか」「どういう働き方が望ましいか」を明確に伝えられるようにすることで、前向きな評価に繋がる可能性もあります。自己理解の深さは強みになります。
Q3. 自分の特性がまだよくわかっていません。どこから始めればよいですか?
A. 自分の特性を知るためには、まず過去の職場や生活で「うまくいった場面」「困った場面」を整理してみることが有効です。必要に応じて、支援機関や専門職(臨床心理士、精神科医、キャリアコンサルタント等)のサポートを受けながら特性理解を深めることもおすすめです。
Q4. 職場の人に発達障害のことを伝えるべきでしょうか?
A. 開示にはメリットとデメリットがありますが、適切に配慮を求めるためには、ある程度の情報を共有することが有効です。伝える際は「どのような特性があり」「どんな配慮があると業務に集中できるか」を整理しておくと、職場とのコミュニケーションがスムーズになります。
Q5. どんな働き方が自分に合っているのか、まだはっきりしていません。
A. はじめから“ぴったり”の働き方を見つけることは難しいかもしれません。実際に職場体験や実習、短時間勤務などを通じて試行錯誤しながら、自分に合う業務や環境を見つけていくことが現実的で効果的です。焦らず、少しずつ自分の「働ける形」を見つけていきましょう。