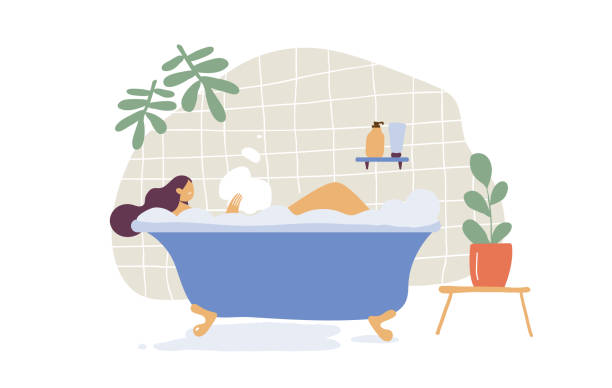適応障害の復職後に欠勤してしまう際の会社への伝え方|クビや再休職のリスクを避け、キャリアを守るためのステップ
適応障害からの復職は、回復の大きな節目である一方、実際の職場環境に再び身を置くことで心身の負荷が想定以上に表面化することも少なくありません。復職後に欠勤してしまい、「評価が下がるのではないか」「再休職や契約終了につながるのではないか」と強い不安を抱える方は多いでしょう。
本記事では、会社への適切な伝え方とリスクを最小限に抑える考え方を整理し、長期的にキャリアを守るための実践的なステップを専門的な視点から解説します。

適応障害と復職後に起こりやすい欠勤の背景
目次
適応障害は、特定の環境や出来事に対する心理的・身体的反応として発症します。復職後に欠勤が生じやすいのは、原因となった職場環境そのもの、あるいは似た刺激に再びさらされることが多いためです。業務量や人間関係、評価制度などが表面的には変わっていなくても、本人のストレス耐性が完全に回復する前に負荷がかかることで、症状が再燃するケースがあります。
重要なのは、復職後の欠勤が意欲の低下や自己管理不足とは本質的に異なるという点です。医療的には、回復過程における揺り戻しとして説明されることが多く、一定の確率で起こり得る現象です。この理解を前提に行動を組み立てることが、不要な自己否定や判断ミスを防ぐ土台になります。
復職後の欠勤が評価や雇用に与える影響
復職後に欠勤が発生した場合、会社側が注目するのは欠勤そのものよりも再現性と説明可能性です。突発的で理由が不明確な欠勤が続くと、業務継続性の観点から懸念を持たれる可能性があります。一方で、医師の見解や体調の経過が整理され、今後の見通しが共有されている場合、評価への影響は限定的になる傾向があります。
クビや再休職に直結するかどうかは、欠勤日数よりも対応の仕方に左右されます。特に日本の雇用慣行では、合理的配慮の検討や配置調整の余地が残されている場合が多く、本人が沈黙したまま状況を悪化させることの方がリスクになります。
欠勤時に会社へ伝えるべき基本原則
適応障害で復職後に欠勤する際の伝え方には、いくつかの基本原則があります。第一に、事実と解釈を分けることです。体調不良で出勤が難しいという事実と、迷惑をかけているに違いないという推測は切り離して伝える必要があります。
第二に、医学的根拠を軸にすることです。自己判断で詳細な心理状態を説明しようとすると、かえって誤解を招くことがあります。主治医から本日は安静が必要と指示されているというように、第三者の判断を含めることで説明の客観性が高まります。
第三に、連絡のタイミングと手段を一定に保つことです。連絡が遅れたり、毎回異なる表現を用いたりすると、不安定さが強調されてしまいます。簡潔で一貫した文面を用意しておくことが、信頼維持につながります。
避けるべき伝え方と誤解を生む表現
復職後の欠勤時に避けたいのは、過度な謝罪や感情的な説明です。「本当に申し訳ありません」「自分が情けないです」といった表現は、誠実さのつもりで使われがちですが、業務上の判断材料としては不要であり、かえって不安定な状態という印象を強める可能性があります。
また、「しばらく様子を見ます」「行けたら行きます」といった曖昧な表現も注意が必要です。会社側は業務調整を行う必要があるため、可否が不明確な表現は負担になります。欠勤が確定している場合は、その事実のみを明確に伝える方が結果的に評価を下げにくくなります。
再休職や契約終了のリスクを下げるための実務的対応
欠勤が一度きりで終わらない可能性を感じた場合、早い段階で中長期的な対応を検討することが重要です。具体的には、主治医と現在の業務量が適切か、勤務時間や業務内容の調整余地があるかを整理し、その内容を会社と共有する準備を進めます。
復職後の欠勤を点で終わらせず、経過として説明できる状態を作ることがポイントです。診断書や意見書は、休職のためだけでなく、就労継続のためのツールとして活用できます。会社にとっても、合理的な判断材料がある方が対応しやすくなります。
キャリアを守るために今できる準備と視点
適応障害の復職後に欠勤を経験したとしても、それ自体がキャリアの終わりを意味するわけではありません。重要なのは、現在の職場でどのような条件であれば安定して働けるのかを言語化できるようになることです。この整理は、社内調整だけでなく、将来的な職務選択においても大きな資産になります。
環境調整や段階的な就労を視野に入れ、自身の特性と働き方を再設計する視点を持つことが、長期的な安定につながります。復職後の欠勤は失敗ではなく、必要な調整点を示すシグナルとして捉えることが、結果的にキャリアを守る最も現実的な選択となるでしょう。